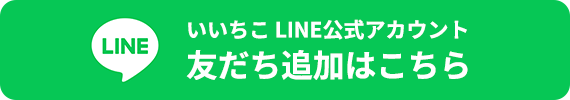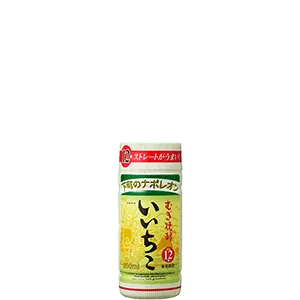太古の昔に偶然生まれ、人類の歴史とともに進化してきたお酒づくり。それを分析し磨きあげ、再現性を持たせてきたのが科学の力です。そんなサイエンス面から「いいちこ」を支える三和研究所員に聞いた、おいしさの秘密・秘訣とは? 今回は「原料」について解説していただきます。

この人が解説!
佐保丞太朗(さほじょうたろう)さん
三和研究所 アートサイエンスパーク 研究室
焼酎にとってどんな大麦が適しているかなどの原料研究、使用する大麦の選抜試験、大麦の新たな価値研究などを行う、原料のスペシャリスト
Q1.麦焼酎の原料はどんなもの?
大麦は、まず皮付き麦、裸麦といって、皮裸性(実と皮の剥がれやすさ)で2つの分類があり、さらに、穂に穀粒が2列に並ぶ二条大麦、6列に並ぶ六条大麦があり、これらの組み合わせで4つの分類があります。
「いいちこ」の原料は皮付きの二条大麦です。

Q2.おいしい焼酎のために必要な大麦の条件は?
焼酎の原料としての大麦の適性には3つの条件があります。
栽培のしやすさ〈農業適性〉
これは焼酎の原料に限った話ではありませんが、たくさん収穫できる品種であること(単位面積当たりの生産高の高さ)、風などで倒れにくい性質をもっていること(倒伏耐性/とうふくたいせい)、病気になりにくいこと。また稀ではありますが、麦が実っているときに雨が降ると、穂に実がついたまま発芽してしまう穂発芽(ほはつが)という現象があるのですが、それが起きにくいことなどが挙げられます。
割れ麦の発生しにくさ〈搗精(とうせい)適性〉
搗精とは穀物の外皮部を剥くことで、その結果できるものをお米なら精米、大麦なら精麦と言います。搗精をしたときに割れ麦が発生しにくい大麦を搗精適性があると評価します。割れ麦が多いとなぜよくないかというと、大麦の粒揃いが悪くなることで、仕込みの際に発酵が不均一になることが懸念されるためです。粒の大きさが揃った大麦を使って、均一な発酵を促すことが良い焼酎づくりには重要です。
発酵工程での働き〈醸造適性〉
大麦は麹菌の力で糖に分解され、それを酵母がアルコールに変え、蒸留を経て「いいちこ」の原酒ができあがります。よって、麹菌が繁殖しやすいかどうか、大麦のもつデンプンからどれくらい効率よくアルコールをつくることができるか、そして、ただ単なるアルコール水溶液ではない、おいしいと感じられる香味バランスを持った麦焼酎が実際につくれるのかどうか。これらが焼酎醸造適性を評価するうえで、重要なファクターとなります。
この3つの適性をすべて備えているものを“良い焼酎用大麦”と定義し、日々分析や選抜を行っています。

Q3.大麦の品質は焼酎の味わいにどのように影響する?
さきほども少し触れたようにおいしいと感じられる焼酎になるには、大麦のもつデンプン、タンパク質、粗脂肪(食品などの脂溶性物質)のバランスが大事なんです。
デンプンを麹が分解して、できた糖を酵母が食べてアルコールを作る、というのがアルコール発酵の大まかな仕組みです。このときに酵母が作るのはアルコールだけでなく、さまざまな香気成分です。このアルコールと香気成分が、蒸留によって取り出されて焼酎になりますが、大麦のタンパク質の多寡(たか)が、焼酎のフルーティーな香りと相関性があることが研究で分かっています。
「いいちこ」はいくつかの原酒をブレンドしてつくられますので、原料担当として、この知見をもとに良い香りをもたらすタンパク質量を見極めて、各原酒のコンセプトに合わせた原料選びを行うことが重要なミッションとなります。
Q4.日本酒の大吟醸のように大麦を磨くことはある?
通常の仕込みでは、収穫された大麦が10割だとしたら、そこから3割ほど搗精した精麦を使用しています。
「いいちこ」ブランドの中でもっともプレミアムな商品である「いいちこフラスコボトル」は、通常の精麦歩合からさらに1割ほど搗精した大麦を使用しています。精麦歩合だけではなく、複合的な技術を使ってはいますが、「いいちこ」のもつ爽やかさがさらに際立ち、澄んだ香りの焼酎に仕上がっています。
日本酒づくりにおける吟醸酒仕込みでは、精米歩合を極端に低くした原料米を使用することが多く、原料の大部分を削る目的は、米粒の外周部分に多く含まれるタンパク質を除くことで、雑味を抑え、かつフルーティーさや華やかな香りが前面に出た日本酒を作ることにあります。
一方で焼酎づくりにおいて精麦歩合を低くした大麦を使う理由は、雑味を抑える目的ではなく、酵母の代謝によってできる代謝産物のバランスを変え、その後の蒸留における成分の抽出バランスを変えることにあります。これは当社の先輩研究員たちによる研究により辿り着きました。
また、大麦は米よりも仕込みの際の吸水によって粒同士がくっついて離れなくなる「しまり」という現象が起きやすく、これは精麦歩合を低くすると、より強まる傾向にあります。これにより製造現場での作業性が悪化し、また発酵における不均一性を助長することになり、仕込みの難易度が上がります。つまり「いいちこフラスコボトル」は研究の積み重ねと製造現場の努力の賜物なのです。

Q5.大麦という農作物をコントロールするのは大変なのでは?
「いいちこ」は豪州産、国産の皮付き二条大麦品種を使用しています。豪州は農業大国であり、大麦の一大産地。ウイスキーやビールといったお酒のための大麦づくりの経験も豊富です。そんな豪州の定めるモルト用大麦の中から、さらに焼酎づくりに適したものを「Shochu」グレードとして厳選していただき、調達しています。
農作物のコントロールは、ひと言でいえば大変です。同じ品種でもその年の気候によって出来が変わってきますし、特に2024年は世界的な異常気象で農産物が収穫できないなどのニュースもありました。幸いにして大麦は、豪州が技術も高く生産量も多いので、「いいちこ」がつくれるかつくれないかというような窮地に陥ることは今のところありません。
豪州は農業大国だけあって、品種の開発や切り替えのスピードも速いです。品種が切り替わるごとに分析して特性を見極めることも研究所の重要な役割です。
実際に入荷する大麦の品質については、豪州から船で輸入されてくる実物の大麦を事前に空輸して分析し、データを見ながら仕込みに活用しており、お客様にいつもおいしいと言ってもらえるような「いいちこ」をお届けするために、日々努力しています。

Q6.最後に原料担当の方からメッセージをお願いします
葡萄酒のブドウのように、日本酒の酒米のように、麦焼酎の大麦にも、年度差や、品種差がある中で、当社では「良い焼酎は良い大麦から」という信念をもって毎年の大麦の安定的な調達に真剣に向き合っています。
そのようにして選ばれた大麦を、製造場の蔵人たちの品質第一とした造りで練り上げ、皆様にお届けしています。これからも最高品質を追い求め、また、技術の革新による新たな価値提供ができるように原料研究を続けていきます。

※記事の情報は2025年1月28日時点のものです。