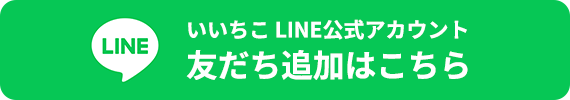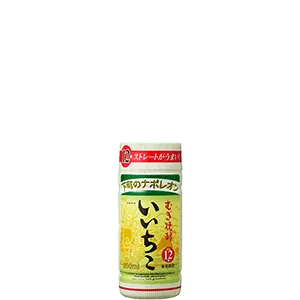初心者が一人でバーに行っても大丈夫? 一人でも入りやすいお店の選び方は? どんな風に注文したら? ソロで心置きなくバーを楽しみたい方のために、渋谷で22年、バーを経営するベテラン・バーテンダーの鈴木健司さんにお聞きしました!

この方にお聞きしました
鈴木健司(すずきけんじ)さん
バーテンダー。BAR AdoniS(バー・アドニス)、Bar Rocaille(バー・ロカイユ)、BAR OLDPAL(バー・オールドパル)を運営する有限会社バッカス代表取締役。東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)洋酒部門の審査員も務める。
バーと言ってもいろんなタイプがある
バーと名のつくお店にはさまざまなタイプがあります。
1つ目はオーセンティック・バー。オーセンティック(authentic)という名の通り正統派のバーのこと。たくさんのお酒が揃っており、バーテンダーが質の高いお酒を提供してくれる、落ち着いた雰囲気のバーです。
2つ目はカジュアル・バー。料理が主体のダイニング・バー、1杯ずつ料金を払うショット・バー、ビリヤード設備があるプール・バー、大画面でスポーツ観戦をしながらお酒が楽しめるスポーツ・バー、音楽が聴けるミュージック・バーなど、気軽に入れるのが特徴です。
3つ目は専門バー。ワイン・バー、モルト・バーなど特定のお酒を専門的に扱います。
今回の記事では、バー初心者にはちょっとハードルが高いと感じられるオーセンティック・バーについて、バーテンダーの鈴木健司さんに教えていただきます!

一人でも行きやすいバーの選び方は?
―プロから見て、初心者が一人で行きやすいオーセンティック・バーとはどんなお店だと思われますか? ホテル内のバーがおすすめという話も聞きますが…。
鈴木:ホテルのバーは安全で会計も明朗なので安心だよね、という話は私も聞いたことがあります。ただ自分がお酒を飲み始めた頃にホテルのバーに飛び込めたかというと、レベルが高すぎて難しかった記憶が…(笑)。
ホテル以外で見つけるときの目安は、同じ場所で長年バーを営んでいるお店、でしょうか。お客様に信頼していただいているからこそ存続できていると考えることができます。あとはエントランスが清潔なお店。掃除が行き届いているバーはホスピタリティが高いことが推測できます。
周りのお酒好きの方に聞いたり、インターネットで検索したり、ある程度下調べをしたら、まずは「エイヤ!」と一歩踏み出していただいて、最初の一軒は「次のバーのヒントを得る場所」と捉えてもいいかもしれませんね。そう考えると、もし一軒目が自分に合わなかったとしても、それは好みのバーを見つけるための1つの経験になります。
一軒目に飛び込めたら、ぜひバーテンダーと会話をしてみてください。バーテンダーは横の繋がりが強いので、きっとその方に合いそうなバーを紹介してくれると思います。私もお客様とそんな会話をすることもありますが、どんな口コミサイトより確かな情報だと自負しています。

一人でバーに行くときに気をつけたいポイントは?
―オーセンティック・バーを訪れる際に、服装やふるまいなど、どんなことに気をつけたらいいのでしょうか?
鈴木:まずは服装ですが、難しく考えず、少しだけ“かっこつける”くらいの気持ちでいいと思います。例えば男性ならジャケットを一枚羽織る、女性ならお気に入りのアクセサリーを一つつける。少しかっこつけることで自分を律することができ、バーの空間をより楽しむことができるのではないでしょうか。
―香水などはどうでしょうか?
鈴木:おしゃれや身だしなみとして香水をつけることはとても素敵なことではありますが、お酒は香りを楽しむものでもありますので、それを邪魔しない程度の配慮は必要かなと思います。
―料金についても教えてください。チャージ料やサービス料といった、いわゆる居酒屋では聞き慣れないシステムもお店によってはありますが。
鈴木:これはお店によって本当にさまざまです。私のお店ではチャージ料はなく、表示価格に消費税も含まれています。平均的な目安としては、カクテルを2杯くらい飲んで4000~5000円くらいのお客様が多いですね。
バーで提供されるものは、心地よい空間、上質なサービス、グラスやおしぼりに至るまで付加価値が含まれ、その付加価値に対して料金が発生します。その分、「バーに来てよかった」と思っていただけるよう努めています。
店内でのふるまいとしては、泥酔しない、騒ぎすぎない、店のルールを守るといった、公共の場でのマナーと一緒と考えていただければよいかと思います。
バーテンダーの役割は?
―バーにおけるバーテンダーさんの役割とはどんなものでしょうか?
鈴木:バーテンダーはバーの番人、世話人であり、同時に調理人であり、サービスマンでもあります。バーという空間全体をコントロールする存在です。常にホスピタリティ・マインドを高く持ち、お客様に寄り添ってお好みの一杯を見つけたいと思うバーテンダーは多いはずです。
バーテンダーの後ろの酒棚をバック・バーと呼びますが、ここに置いてあるお酒については何でも聞いていただければと思います。実際、「あのかわいいボトルは何のお酒ですか?」と聞かれたりしますよ。そういった意味ではお酒のコンシェルジュと言えるかもしれません。
コンシェルジュと言えば、バーテンダーは街のコンシェルジュでもあるんです。「これから食事に行くんだけど…」とおすすめのお店を聞かれたら、みんな一生懸命考えてくれると思います。そういった情報収集も普段からしているバーテンダーは多いのではないでしょうか。

飲み物をスマートに注文するには?
―初心者が飲み物をスマートに注文するコツなどはありますか?
鈴木:スマートに注文しようと気負う必要はありません。むしろ、バーテンダーとのコミュニケーションを最大限に活用することが、実は一番スマートな方法です。
私たちバーテンダーはお客様にとって最高の一杯を提供したいと思っています。そのためにはお客様の好みやコンディションといった情報が必要なんです。「喉が渇いている」「アルコールの強さはこれくらい」「酸味や炭酸の好み」など、どんな些細なことでも構いませんので、恥ずかしがらずに伝えてください。そうした対話の中から、お客様にぴったりの一杯を見つけ出す。いわばお客様とバーテンダーとの共同作業ですね。それこそがバーの醍醐味だと私は思います。
お酒が弱い、あるいは今日はお酒が飲めない、という方には「モクテル(ノンアルコール・カクテル)」もおすすめしています。「モック(mock=真似る)」という言葉の通り、お酒の風味や雰囲気をどう再現するかがバーテンダーの腕の見せどころです。アルコールを飲まないという選択も、とてもスマートだと思います。
バーがもっと楽しくなるカクテルの基礎知識
―カクテルのことを少し知っておくと、バーの楽しみ方も深まるように思います。基本的なことを教えていただけますか?
鈴木:まずカクテルとは、「2つ以上の材料が混ざった飲み物」のことです。なぜカクテル(cocktail)というのかは諸説ありますが、私が好きなのは、昔バーテンダーがグラスのお酒をオンドリの尻尾(羽根)で混ぜていたら「それ何だ?」と聞かれて、お酒の方だと思わず「cock tail=オンドリの尻尾」と答えたのが広まったというものです。
カクテルの大きな分類としては、「ショート・カクテル」と「ロング・カクテル」があります。ショート・カクテルは小さめの脚付きグラスに注がれたもので、温度が上がらないうちに飲みきるのがおすすめです。ロング・カクテルはアルコール度数が比較的低めで氷が入っており、比較的長い時間をかけてもおいしく味わえます。

作り方でも分類ができます。ベースとなるお酒に柑橘系のジュースを加え、炭酸飲料で割ると「クーラー」、ベースとなるお酒に酸味や甘味を加えると「サワー」、ベースのお酒をソーダで割ると「ハイボール」というようにいくつかのスタイルがあります。
マティーニやギムレットといった、どのバーでも取り扱いがある定番のスタンダード・カクテルと、その店独自のオリジナル・カクテルという分類もあります。

―カクテルのベースとなるお酒にはどんなものがありますか?
鈴木:蒸留酒ではウオッカ、ジン、テキーラ、ラム、ウイスキー、ブランデー、醸造酒ではワインやビールが定番です。焼酎を使うバーも多くなってきました。近頃はバック・バーに置いてもなじむデザイン性の高いボトルの焼酎も出ていますので、可能性を感じています。スタンダード・カクテルのベースを焼酎に変えたらおもしろいなとも思います。なんと言っても焼酎や日本酒は我々の文化ですし、日本の方はもちろん、海外の方にもどんどん紹介したいですね。
バーで楽しむ「いいちこ」が登場!
バー文化の本場アメリカから販売をスタートし、約6年の時を経て、2025年6月から日本での販売が開始された「iichiko彩天」。ウオッカ、ジン、テキーラ、ラムといったカクテルベースの主流となっている世界の蒸留酒と肩を並べるアルコール度数43度という高度数と、大麦麹から生まれる深いうまみ、カクテルの魅力を引き立てる豊かなフレーバーです。
バック・バーで見つけたら、「iichiko彩天」を使ったカクテルをぜひお試しください!

※記事の情報は2025年7月8日時点のものです。